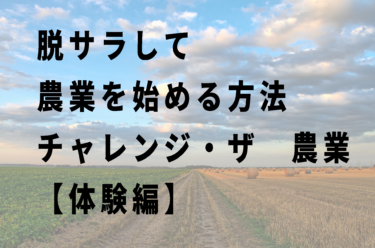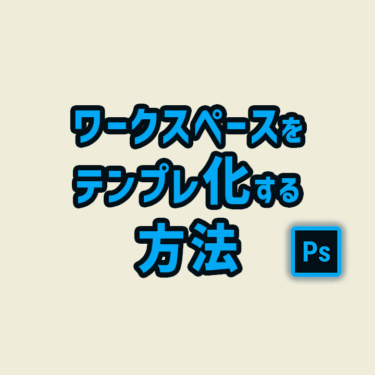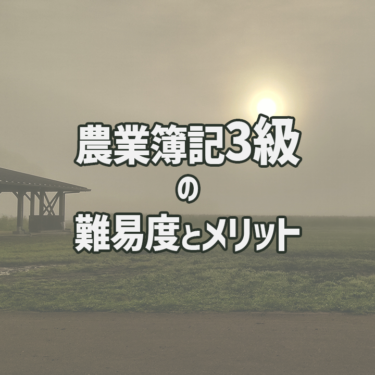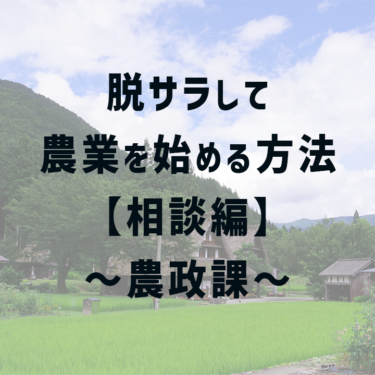こんにちは。こばやしです。
脱サラして就農する場合、非農家の方の多くは学校に通うことになると思います。
- 就農準備校ってどんなところかわからない方
- 就農前に学校に行きたいけど悩んでいる方
↓入学の前に農業体験したい方はこちらをご覧ください。
こんにちはこばやしです。 行ってきました。農業体験。 今回は5日間の短期体験です。 結論というか私の率直な感想を申し上げますと、 いけるなら絶対行った方[…]
私は茨城県の就農準備校に入学しました。
創立95年の歴史ある学校のため、今までの就農者も今後の就農予定者も多くの方が経由する就農方法になると思いますので、今後も経緯を投稿していきます。
就農準備校ってどんなところ?
就農準備校については、この記事を参照ください。
実際に入試、入学手続きまでの経緯を記載しています。
こんにちは。こばやしです。 脱サラして就農するにあたって、何から始めていいかがわからず戸惑いますよね。 Aさん 就農準備校ってどうなの? Bさん どうやった[…]
就農準備校のメリット
農家になるために必要な知識を習得できる
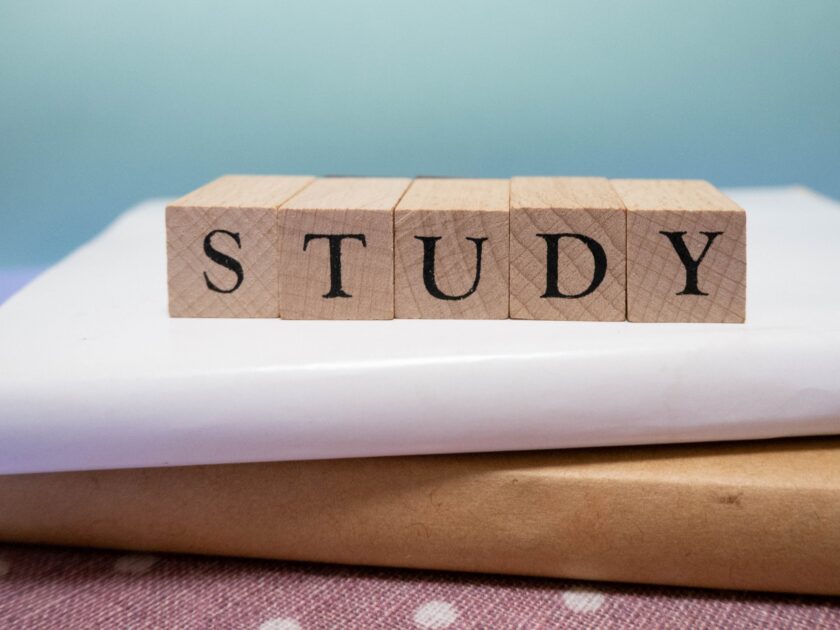
日本農業実践学園では以下のような資格や知識を習得できます
- 大型特殊免許(農耕車限定)
- 農業簿記(3級・2級・1級)
- 土壌診断(土づくりマスター・土づくりマイスター・土壌医)
- 日本農業技術検定(3級・2級・1級)
- 小型車両系建設機械特別講習
- 養蜂技術
この他有機栽培技術や多くの知識を習得できます。
こんにちは。こばやしです。 今日は何かと使用頻度の高いマルチについて書きます。 マルチとはなんぞや?な方 家庭菜園などでもマルチが必要なことがわかってはいるがはり方がわからない方 せっかくマルチを張るなら[…]
こんにちは。こばやしです。 今回は播種について書いていきます。 私は、「はしゅ」と言われても初めはなんのことかわかりませんでした。 作業としては頻繁に行われますので、これを機に覚えてしまいましょ[…]
↓(参考)2021年度の専門士科のカリキュラム一覧です。
学生圃場で実践的な練習ができる

実際の写真です。
学生一人一人に圃場(畑)が貸与されます。
社会人コースの養成科では一人2a(200㎡)程度が与えられます。
自分で好きな作物を選択し、自分の責任で栽培します。
実践経験を積めるいい機会です。
先輩農家さんや就農支援機関とのつながりができる
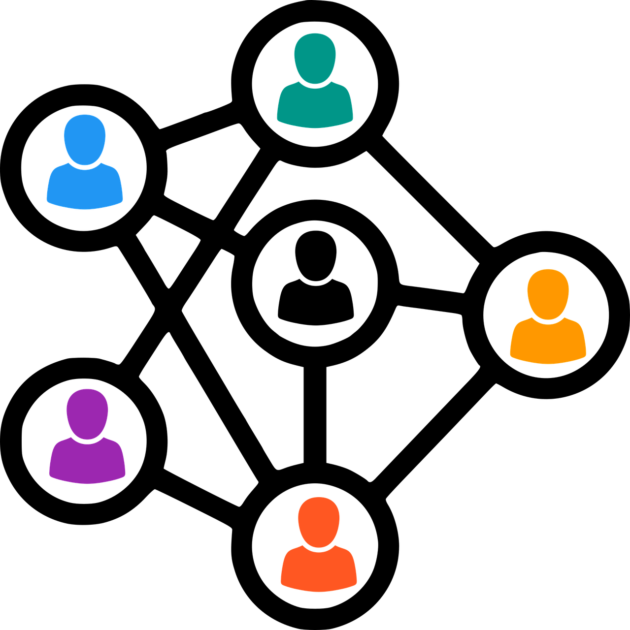
卒業生や先生方の知人、地域のつながりなどの輪の中に入れます。
非農家が農家の輪に入るのはかなりハードルが高く、実際に飛び込みで話しかけても成功率は低いです。
しかし、学生という形で地域の輪にすんなり入ることができます。
また、本気で農業を目指しているということを理解してもらいやすくなります。
365日農業に触れ合える
原則全寮制で敷地内に学生圃場があるため、ご自身の計画次第では、土日でも畑いじりができます。
夕方は街灯などはないため、作業は難しいです。
図書館などを利用して農業の書籍も閲覧することができます。
また、農業専門の出版社が出張販売所なども不定期で開かれています。
学校によっては補助金の申請ができる
就農するために補助金が出る制度があります。
制度自体に毎年変更が加えられているため、最新情報の確認は欠かせませんが、
学校によっては研修機関と認められていれば補助金の申請ができる場合があります。
補助金なので、審査があります。
そのため、申請すれば全員がもらえるわけではありませんが、採択されれば、2022年の場合は年間150万円が最長2年間もらえます。
もらった後も一定の条件をクリアする必要がありますが、もらえれば非常に助かります。
就農準備校のデメリット
自分の頑張り次第

就農準備校の社会人コース(養成コース)は通常の学校とは異なり、
かなり学生の自主性によって学習内容が左右されます。
さぼろうと思えばいくらでもさぼれますが、習得できる内容は少ないです。
しかし、周囲の人よりも農業に取り組むことで、少ないリスクで農業にチャレンジできます。
また、授業においても積極的に自分事に置き換えて質問するなどすることでより知識を吸収することができます。
1から10まで教えてもらいたい方にとってはなかなか実りある学校生活は難しいかもしれません。
しかし、そういった方は独立自営にも向いていないと思います。
学生生活中に直すというのであれば一つの手段としてはいいと思います。
どうしても直したくない方は雇用就農の方があなたには向いています。全寮制のため向き不向きがある
希望する作物のコースがないと少し遠回りすることになる
ご自身がやりたい作物のコースがないと、将来やりたいことと少し異なることも学びます。
例えば、ハウス栽培でイチゴをやりたいのに、有機栽培で露地のブロッコリーを育てたり。
「やりたいことはそれじゃないのに」と思うか、「実際に就農するまでにいろいろな情報を入手できる」と考えるか、人それぞれです。
最短距離を突き進みたい場合は、自分のやりたい作物のコースがあるかしっかり確認してください。
明確に決まっていない場合は、就農までに時間をかけて情報収集できることは逆にメリットになります。
実際やってみるとブロッコリーも楽しいかもしれません。
就農予定地が遠いとつながりが生かしきれない
例えばあなたが西日本で就農を希望している場合、
茨城県にある学校からではつながりをつくりにくいということがデメリットです。
近隣であれば訪問するなどして、きっかけを拡げることができます。
しかし、遠方であれば、オンラインやテキストでのやり取りが増えます。
学校から得られるつながりを最大限生かすには、ご自身の行動力が伴わないと厳しいです。
全寮制は好き嫌いがある

学校は全寮制です。
実際に割り当てられた8畳ほどの部屋。
就農準備校は朝が早く、活動時間を確保する視点からも、ほかの就農準備校も全寮制の学校が多いです。
新設校でもない限り、多くの学校の設備は年季の入ったものが多いです。
トイレも和式など、不慣れな生活を送るかもしれません。
寮生活が苦手な方にとってはデメリットかもしれません。
まとめ
今回は就農準備校がどんなところで、どんなメリット・デメリットがあるのかをお伝えしました。
間違いなく言えることは、
就農準備校が有意義かどうかは、あなたの努力次第です。
教えてもらえないなら、自ら質問しましょう。
少しでも授業がわかるように、本を読んで予習しましょう。
それでもわからなければ質問しましょう。
卒業しても進学するわけでもなく、テストもありません。
あなたの将来がかかっています。
誰かに任せるのではなく、自分でイメージ通りに作り上げえていけば、
きっと実りある学園生活になります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。