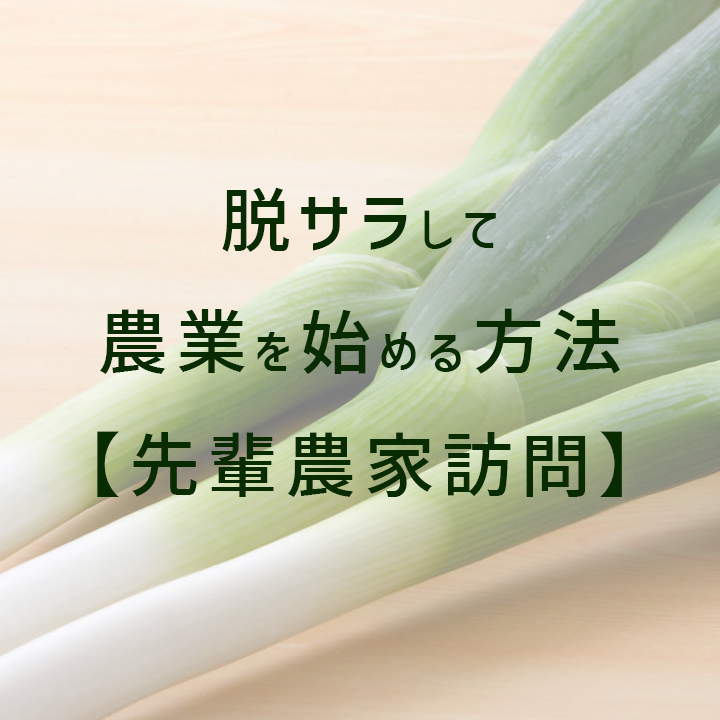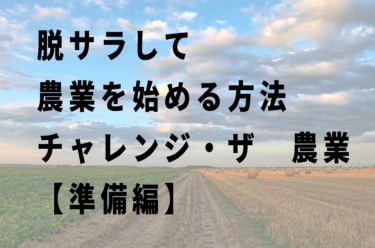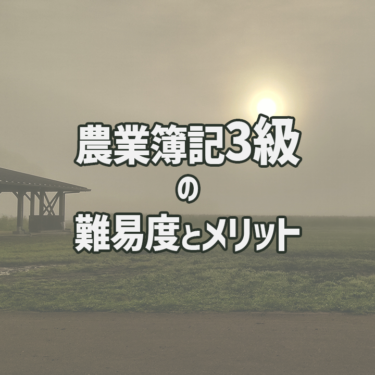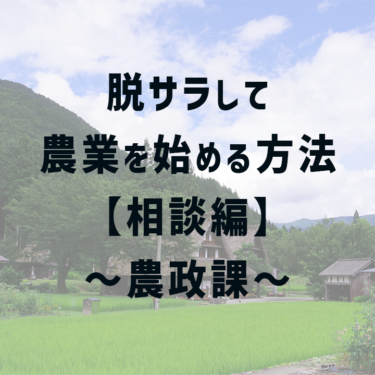こんにちは。こばやしです。
確かに、非農家出身だとなかなか先輩農家にお話を聞く機会はないかもしれません。
そこで今回は茨城県農林振興公社でのご紹介を受けてとあるネギ農家さんをお伺いしました。
- 作物の決め方と情報収集の仕方について
- 就農して難しかった点、失敗した点
- 就農後の1日のタイムスケジュール
- 非農家から就農するにあたって気を付けたほうがいいこと
- 自己資金など、どれくらい準備して、初期費用はどれくらい?
- 農業所得と手取りの違い
- 販路はJAがメインですか?
実際に先輩農家さんがどんな働き方をしているかなどのイメージを持っていただけると思います。
2024年、非農家出身の私がいちご農家として新規就農しました。「農業を始めたいけれど、何から手をつければいいのか分からない」「土地も経験もない自分にできるのか?」そんな不安を抱えていた過去の自分に向けて、そして同じような悩みを持[…]
こんにちは。こばやしです。 今回は脱サラして就農するために、初期段階でする情報収集についてです。 就農の相談窓口としてはこの記事をご覧になってください。↓ [sitecard subtitle=関連記事 url=https[…]
作物の決め方と情報収集の仕方

作物は自由に決めていい
今も昔も自治体としては、坪単価の良いいちごを勧めているようですが、結論としては、作物は好きなものを育てたらいい。
ということでした。
その農家さんが就農したときは水菜が流行っていたそうです。
こぞってみんなが水菜を育てたので、水菜の単価は下がってしまったそうです。
その方も初めはイチゴを検討していたけれど、いろんな農家さんを見て歩くうちに、イチゴはとても手間暇がかかる作物だと感じ、比較的栽培しやすいネギを選択したそうです。
もともとネギが好きだったことも大きな要因だそうです。
目指している農業スタイルや、収支、労働時間などは人によって本当に様々なので、一概にどの作物がいいとは言えない。
いろいろな農家を見て自分で決めるのが一番良い。ということでした。
その中でとても興味深い言葉が、「農家は飲食店と同じで、高級料理店もあれば大衆居酒屋もある。農業と聞くとなぜか1パターンだと思い込んでしまうが、農家一人ひとりでスタイルは全く違う。」というものです。
まさに、1パターンだと思い込んでいた私は衝撃でした。そんな簡単なことにも気づけないくらい思い込みといものは怖いなぁとつくづく感じるのでした。
情報収集の第一歩は町の一員になること
ほんと、これに限る。とのこと。
早い段階でその町の一員になれるかどうかで就農の難易度が変わるとおっしゃっていました。
研修先の町や、就農希望地において、愛想がいいことは必須条件といっても過言ではない。
自分が町の人を知らなくても、相手は自分を知っているので、どんな方であっても挨拶は欠かさなかったそうです。
そうこうしているうちに、こんな集まりがあるよ。必要ならこの道具あげるよ。など情報が集まってくるようになるそうです。
就農前の段階では、実際にいろんな農家を見て歩くことが重要だと教えてくれました。
先輩農家さんにお伺いすると、その方が所属しているコミュニティがあるので、それを紹介してくれることもあるようです。
就農して難しかった点、失敗した点

今でも失敗はするし、失敗することはダメなことではない
失敗しないと正解に近づけないから、実際に失敗した原因をきちんと考えることが大事だと教えてくれました。
毎年気候が違ったり、災害があったり、育苗がうまくいかなかったりというリスクはある。
運ではなく、リスク管理次第なので、「基本的に悪いのは自分」。
農家になるということは経営者になるということ。
結果を誰かや何かのせいにしても状況は変わらないということで、すべての原因は、判断した自分にあると考える。
1日のタイムスケジュール
![]()
働き方は自分次第
私がお伺いしたその日は朝の9時から作業を開始したそうです。
思っていたより遅いんだな。というのが私の感想です。
農家は早朝から作業するものだと思っていましたが、この農家さん曰く、それも自分次第だよと。
夏の暑さが大丈夫なら、日中仕事してもいいし、つらいなら早朝仕事すればいいし。
ただ、通常日が暮れたら仕事ができないのは農家さんでは主流ですが、朝ゆっくりした日は、電気をつけて夜に仕事をしなければならないこともあるそうです。
作物によって全然違うのでどんな生活を送りたいかで作物を検討することも大事かもねとのことです。
仕事の仕方は本当に自分次第。研修で農家さんに行くと法人or個人で違ったりはするので、そこも自分に合うかどうかを確認するといいとおっしゃっていただきました。
非農家から就農するにあたって気を付けたほうがいいこと

基本的に事前に準備できることは全部やっておいたほうがいい。
学校がいいですか?農家研修がいいですか?という問いに
それぞれにいいところがあるので、できるならどっちもやってください。と。
事前の研修をやらなくても、学校に行かなくても就農している人はいます。
しかし、実際に就農してからの成功率が変わってきます。
なので、就農前にできることがあれば、農業体験でも営農塾でもできることは何でもやってくださいということでした。
ひたむきに研修を受けていると、周辺も「頑張っている」と認めてくれやすいという面もあるよ。と
就農地には同じ作物を作っている人がいた方がいい
自分の畑の作物の育成度合いを比較できることがメリットで、それがないと出来がいいのか悪いのかも初めはわからないです。
それにわからないことを聞けるということはとても大きな武器になるそうです。
できるだけ近くに住んだ方がいい
親元就農の方などは本当に家の目の前に農地がありますが、非農家の方はそうでない場合もあります。
車で10分だったとしても毎日の作業や緊急で農地に行かなければいけない場合など、必要な気力が異なるので、めんどくさい日もあるそうです。
お風呂上りに、ハウスを開けないといけない事態が発生したとしたら本当にだるいそうですw
夜雪が降った場合、ハウスを見に行くなど、徒歩圏内か車で10分かかるかでは労力が違いますよね。
家族で就農するなら同じ目標を持ってやった方がいい
毎日一緒にいるので喧嘩も増えたそうですが、サラリーマン時代と違って何に対して怒っているのかがわかる為、八つ当たりされているというストレスは減ったそうです。
また家族で就農すると、あれもこれもやってあげた方が助けになると思ってなんでも頑張ってしまうが、「やること」と「やらないこと」の線決めはきっちりしておいた方がいいそうです。
その線決めがないと疲れ切るまで仕事してしまうよ。と家族で就農するときの秘訣も教えてくださいました。
自己資金や初期費用は?

自己資金は多い方がいい
その方は若い段階で就農しており、自己資金は200万円ほどだったそうですが、一年でなくなったそうです。
自己資金がないからできないということはないが、自己資金は多ければ多いほど精神的に余裕がでるようですね。
初期費用は全額借入で800万だそうです。露地栽培で50アールで始めたそうですが、鎌一本でも費用が掛かるのであっという間になくなってしまうようです。
町の一員として認められていれば、不要なハウスや農具など譲ってもらえることが増え、安く抑えることができてとても助かるよとおっしゃっていました。
助成金は使えるものはすべて使った方がいい
新規就農にあたって資金を借り入れることはできますが、助成金をもらえるならもらった方がいいということでした。
例えば、令和4年度から農業次世代人材投資資金の出資元が国100%から国50%都道府県50%に変更になる可能性があり、なかなか助成金のめどが立たないことが難しい。
でも使えるものは調べて全部使いましょう。助成金を申請する段階で農林振興公社や農業改良普及センターの方々とのつながりもできてきますとのことでした。
農業所得と手取りとは?
農業では3割取れれば優秀
売上高に対し、手取りが3割残れば優秀という意味だそうです。
1,000万円売り上げがあり、手取りが300万あれば優秀ということですね。
(売り上げ)-(原価・経費)-(社会保険料など)=手取り
作物によって人件費などの経費は大きく変わると思いますので、作物選びの際には農業所得についても検討しなければいけませんね。
販路はJAがいい?

JA以外は儲かる可能性が高い、でもすごい大変なこと
自分で営業して販路を拡大できればその方が儲かるが、それをできる人はなかなかいないと思うとのこと。
最終防衛ラインとして機能しているのがJAという認識だそうです。
ちなみにその方は全数をJAに納品していました。
販路が一つでいいということがとても楽だそうです。
必要経費は掛かるが、それでも所得補償があったして、安心という面ではJAが一番だと思うとのことでした。
JAや直売のメリット、デメリットを考えて自分の目指す農業にはどちらが近いか、という判断次第で販路は変わります。
まとめ
初めての農家訪問でしたがとても気さくで、こういった方のもとで研修したいなと強く思いました。
先輩のおっしゃるように、いろいろな先輩農家を見て回ろうと思います。
農家さんによって考え方は大きく変わるため、どんな先輩がいるのか、自分の目で確かめてみるのもいいと思います。
農林振興公社や普及センター、農政課でも紹介してくれる場合があるようですので、積極的に訪れましょう。
最後まで読んでくださってありがとうございました。