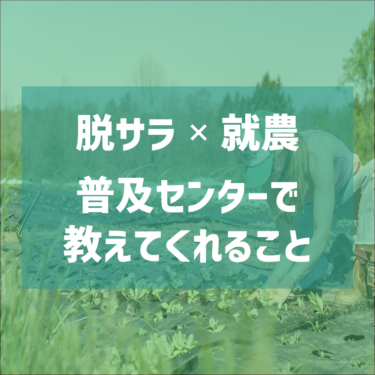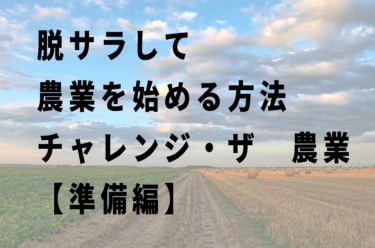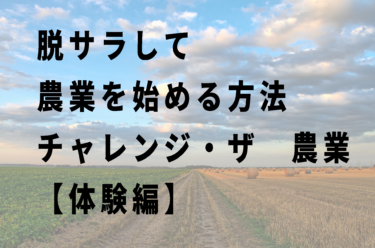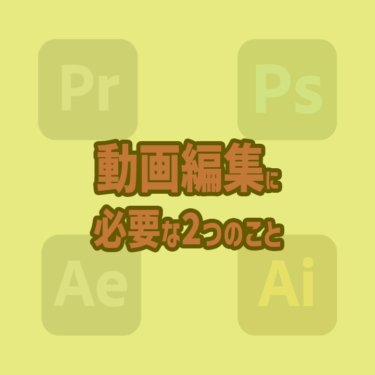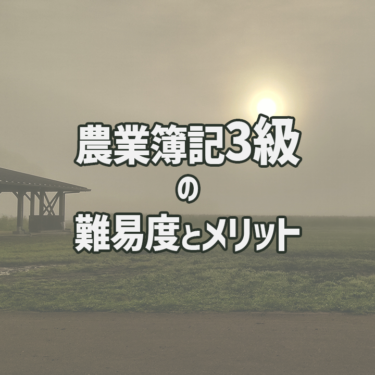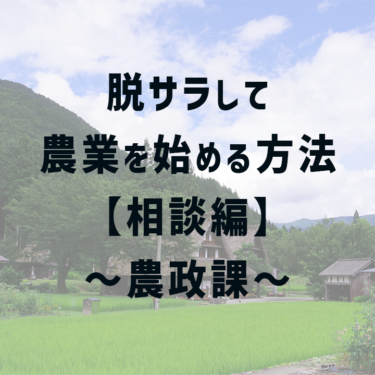2024年、非農家出身の私がいちご農家として新規就農しました。
「農業を始めたいけれど、何から手をつければいいのか分からない」「土地も経験もない自分にできるのか?」
そんな不安を抱えていた過去の自分に向けて、そして同じような悩みを持つあなたに向けて、
非農家から農家になるまでの道のりをステップバイステップでご紹介します。
- 農家になるまでの道筋
- 農家になるために必要なこと
ステップ0:農業への興味を持つ
なぜ農業をやりたいのか?
まずは「なぜ農業をやりたいのか?」を自問自答することから始めました。
また、SNSやYouTubeで農業に関する情報を収集し、現実的なイメージを持つようにしました。
ちょっとやってみる
家庭菜園や農業体験に参加し、実際の農作業を体験することで、農業への興味が本物かどうかを確かめた方がいいです。
こんにちは。こばやしです。
家庭菜園をしたいと思っても庭を掘り返すのが難しかったりする場合があります。
今回は「レイズドベッド」という方法で簡単に家庭菜園を始める方法をお伝えします。
[…]
就農してから、思ったよりしんどかった。みたいにならないようにしたいですね。
ステップ1:情報収集と方向性の決定
どの作物を育てたいのか、どの地域で農業を始めたいのか、自営か雇用かなど、具体的な方向性を決めるために情報収集を行いました。自治体の新規就農相談窓口や国・県の制度(補助金・研修など)を調べ、自分に合った支援策を見つけました。
就農には3パターンある
- 独立就農
- 雇用就農
- 親元就農
独立就農
いわゆる農家さんになることを目指します。自営農業をします。
ほかの業種の起業と同じで、農業を経営します。
技術、農地、資金などを自身で手配して、個人事業主または法人として農業を営みます。
雇用就農
農業法人に就職するといった就農の方法です。
農家になりたいのではなく、農業に従事したい方はこちらを選ぶと思います。
また、独立するための準備期間としてまず雇用就農から始める場合もあります。
農地や資金などは雇用先が持っているので、技術を習得しやすいです。
しかし、就職なので、やりたい作物や栽培方法ができるとは限りません。
親元就農
実家が農家などの場合が該当します。
もともと農家の家系で、それを継ぐ場合の就農方法です。
第3次承継もこちらに近い就農方法です。
就農相談
相談窓口として
- 農業会議
- 市町村の農政課
- JA・農業団体
- 新規就農センター
- 農業フェアなどのイベント
などがあります。
インターネットで「○○(都道府県) 新規就農」で検索してみてください。
茨城県では「茨城就農コンシェル」というサイトにつながることが多いです。
どこに相談するにしても「どこで 何を育てたいか」くらいはざっくり考えておいたほうがいいです。
相談される側も、何を相談されているのかわからなければ答えようがないので、
就農するために必要な資金の目安とか、期間とか、就農したあと生活していけるのか。
とか聞いてみるとイメージがわきやすいと思います。
こんにちは。こばやしです。 今回は脱サラして就農するために、初期段階でする情報収集についてです。 就農の相談窓口としてはこの記事をご覧になってください。↓ [sitecard subtitle=関連記事 url=https[…]
こんにちは。こばやしです。 今回は農林振興公社のご紹介で農業改良普及センターに相談に行ってきました。 [sitecard subtitle=関連記事 url=h[…]
ステップ2:学びと体験
農業大学校や研修機関、アルバイトなどを活用して、実際に農業の現場で学びましょう。
現場での経験は、書籍や動画では得られない貴重な学びとなります。
また、農業次世代人材投資資金などの制度も活用すれば、研修期間中の生活を支えてくれるはずです。
就農準備校の体験研修
各都道府県には農業大学校と呼ばれる学校があります。
大学とは異なり農業を始める人の知識習得の場になっています。
そのほか、農業実践校や民間の学校、JAなどでも体験研修をすることができます。
社会人でも可能なように、1日コースや週末・平日の夜間など比較的通いやすい日程があります。
こんにちは。こばやしです。 前回、先輩ネギ農家さんに訪問して、多くの農家さんを見て回るといいよと助言をいただ頂きました。 [sitecard subtitle=関連記事 url=https://the-beg[…]
こんにちはこばやしです。 行ってきました。農業体験。 今回は5日間の短期体験です。 結論というか私の率直な感想を申し上げますと、 いけるなら絶対行った方[…]
農家での体験研修・インターンシップ
実際にやってみたい作物や地域が決まっているなら農家さんに直接相談することもできます。
ただし、新規就農するには農家さんとつながりがない方がほとんどだと思いますので、
後述する窓口で相談した後に農家さんを紹介してもらうのがよいでしょう。
ステップ3:資金と農地の確保
農業を始めるには初期投資が必要です。
ハウスや機械、苗、土、設備など、現実的な資金計画を立てましょう。
自治体の農政課などと一緒に作成することも多いです。
農地の確保も重要で、農地ナビや農地バンクを活用して、早めの準備と行動を心がけました。
1~2年くらいは様子を見ておくといいかもしれません。
就農に向けて必要なものをそろえる
- 農地
- 住居
- 設備・機械(資金)
農地
農地は、見知らぬ他人にはなかなか貸してくれませんが、農家研修を経て、地域になじむことができれば、その農家さん(師匠))経由で紹介してもらえることもあります。
学校などに通っても近隣の情報を得られることもあります。
ただし、状態の良い農地はすでに既存の農家さんが所有していることが多く、農地の取得が難しいことが課題と言えそうです。
住居
賃貸暮らしであれば農地のある地域に移住をすればよいだけですが、
持ち家の場合はそうはいきません。
現在住んでいる地域で農地を探すのがよさそうです。
フットワークが軽い賃貸の方が選択肢は増えますが、持ち家は地域に根付く準備がしているとみなされ信頼につながる場合もあります。
一概に賃貸、持ち家のどちらがいいとは言えません。
設備・機械(資金)
農家研修を経て、実際に何が必要なのか、資金はどれくらい必要か、
などリアルな数字が見えてきたらそれを参考に準備します。
全国農業会議所全国新規就農相談センターが実施した平成28年度の新規就農者の就農実態に関する調査結果によると、就農1年目の営農資金の平均額は569万円、中央値が300万円だそうです。
またそれとは別に生活費も準備しておかなければいけないのですが、生活費の平均額159万円、中央値が100万円です。
この集計は初期費用が少なくて済む露地野菜から、初期費用がかなり高額な酪農などがすべて含まれているため、数字のまま受け入れるのは危険ですが、一つの目安になります。
ハウスなどを使う施設野菜などは、農業資材の相場によって準備資金が異なりますので、複数の業者から見積もりを取った方がいいです。
私が目指しているイチゴの場合、栃木県農業試験場 いちご研究所が平成24年に出しているいちご新規参入経営支援マニュアルが出している試算だと、初期投資1,400万円(融資含む)+夫婦2人の生活費2年分で600万円が必要としています。
やはり起業なので大きな費用が掛かりますし、農業は成果物が出来上がるまでに期間を要するので、初年度の生活費のストックは必須と言われています。
ステップ4:開業準備
営農計画書の作成、補助金申請、現実的な準備フェーズに入りました。
副業としてブログや動画編集などを始め、収入の柱を増やす工夫も行いました。
土地を取得してすぐには作物を植えられないので、下準備が必要です。
私の場合、耕作放棄地でしたので準備にめちゃくちゃ時間がかかりました。
ステップ5:就農スタート!
いよいよ作付け、収穫、販売と、やることが一気に増えました。
農業は「思った通りにはいかない」ことの連続ですが、それ以上に「やってよかった」と思える瞬間もたくさんあります。
私の場合、苗づくりの失敗、水没、猛暑での不作など、さまざまな困難がありましたが、諦めずに「どうしたら来年は良くなるか」を考え続けています。
まとめ:農業の道は険しく、でもおもしろい
非農家から農業を始めるのは、決して簡単な道ではありません。
それでも「自分で育てた作物を、誰かが笑顔で食べてくれる」その喜びは何にも代えがたいものです。
これからこのブログでは、各ステップをもっと詳しく分解して紹介していきます。
具体的な体験談、失敗談、使った道具、副業との両立の話などもお届けするので、よければ引き続きチェックしてくださいね!